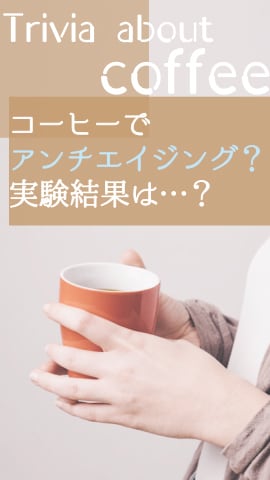ハワイ島コナ産の100%ピュアなコナコーヒーを日本で焙煎。通販で全国にお届け!
◎マークハワイコーヒーのオリジナルコナコーヒー豆(MARK HAWAII COFFEEラベル)は、世界が認める「ファンシー」グレードだけを使用。焙煎したての新鮮な豆(日本国内で焙煎)を、お好きな挽き方・フレーバーで販売します。
輸入製品「ロイヤルコナコーヒー」も販売中です(実績20年以上)。
◎コナコーヒーとは、ハワイ島(通称ピッグアイランドの西側に位置するコナ地区で栽培収穫されたものをいいます。ブルーマウンテン、キリマンジャロと並び、世界3大コーヒーと呼ばれるコーヒーの一つ。とても希少価値が高く、本当にいい豆はとても手に入りづらいことでも有名です。コナコーヒーの特徴についてはこちら→「コナコーヒーとは」
◎ギフトボックスをご希望の場合は、カートに「ギフトボックス」の購入追加をお願いいたします。
※のし紙対応いたします。
LINE友だちでオリジナルコーヒー20%OFFクーポンGET!誕生月クーポン配信
ITEM LIST
-

マークハワイオリジナルコナブレンド | 選べるグラインド5種
¥1,600
ハワイ島コナ産ファンシークラスの豆を丁寧にレギュラーローストしました。 10パーセントハワイ産の豆とマークハワイオリジナルブレンドのさわやかな風味をお楽しみください。 内容量:200g
MORE -

マークハワイコーヒーコナ100 | 選べるグラインド6種、ハワイコナ産ファンシー100%
¥4,500
コーヒー好きなら一度は味わいたい 上級グレードの希少なコーヒー、ハワイ・コナ ハワイコナ(コナコーヒー)は、世界三大コーヒーのひとつに数えられる、高級コーヒーの代名詞。そのコナの中でも人気の「ファンシー」を100%使用した、贅沢なコーヒーです。 豆の等級を判断する基準である、大きさ、形、均一性などすべての点で上級ランクの評価を得ています。 コナコーヒーの中でも傑作と呼ぶにふさわしい、コーヒー通が憧れるコーヒーの味わいをご堪能ください。 内容量:200g
MORE -

アロハフレーバー ・コナブレンドコーヒー | 選べるグラインド5種 | フレーバーコーヒー
¥1,600
アロハな香りでハワイ気分! ハワイコナ産ファンシー10%使用のコナブレンド アロハフレーバーは、当店のオリジナルフレーバー。 ハワイのホテルラウンジで飲むモーニングコーヒーをイメージして香りをブレンドしました。 香りがほんのり甘く漂います。甘過ぎないので、コナブレンド自体の味もしっかりお楽しみいただけますよ。モーニングコーヒーに、特におすすめ。
MORE -

ココナッツフレーバー ・コナブレンドコーヒー | 選べるグラインド5種 | フレーバーコーヒー
¥1,600
南国の海辺が目に浮かぶココナッツの香り ハワイコナ産ファンシー10%使用のコナブレンド ハワイでも人気のココナッツフレーバーは、当店でもリピーターさんの多いフレーバーの一つ。 南国風の甘いココナッツの香りは、ハワイのあの美しい海辺を思い起こさせてくれることでしょう。 アロハスタジアム等のフリーマーケットで冷えた実のジュースを飲んだことが有る方なら、すぐにお分かりいただける香りです。 アロハ〜♪な気分で、幸せなくつろぎタイムをお楽しみください! 内容量:200g
MORE -

チョコレートマカデミアナッツフレーバー・コナブレンドコーヒー | 選べるグラインド5種 | フレーバーコーヒー
¥1,600
ハワイのお土産で定番の、マカデミアナッツチョコレートの香りをコーヒーで! チョコの甘い香りと、ナッツの香ばしさが絶妙です。 "ハワイのお土産"の定番、ハワイアンホーストやマウナロアのマカデミアナッツチョコレートの香りを、コーヒーでお楽しみいただけます。 その深い味わいから「ナッツの王様」と呼ばれるマカダミアナッツの上品な香ばしさと、チョコレートの甘い香りを、絶妙なバランスで組み合わせてブレンドしました。 このコーヒーだけでもまるでデザートのような味わいですが、ケーキなどのスウィーツにもぴったりのフレーバーコーヒーです。 内容量:200g
MORE -

バニラへーゼルナッツフレーバー・コナブレンドコーヒー | 選べるグラインド5種 | フレーバーコーヒー
¥1,600
ふんわり甘く柔らかいバニラの香りとヘーゼルナッツの香ばしさ。 ハワイコナ産ファンシー10%使用のコナブレンドコーヒーの風味、香りがより芳醇に。 内容量:200g フレーバーコーヒーの定番、バニラへーゼルナッツフレーバー。ヘーゼルナッツとバニラは相性が抜群で、愛好者がとても多いフレーバーです。 クッキーやチョコレート、アイスクリームなどのお菓子によく使われるヘーゼルナッツの香ばしさが、バニラの柔らかく甘い香りと交わって、コーヒーの香りをより芳醇に高めてくれます。 生クリームやチョコレートシロップ・キャラメルシロップで、カフェ風のコーヒータイムを自宅で手軽にお楽しみください! 他のフレーバーコーヒーと同様、ほぼノンカロリー。 ブラックでも甘い香りを楽しめるので、お菓子を我慢しているときの気分転換にも特におすすめのフレーバーです。
MORE -

キャラメルバニラフレーバー ・コナブレンドコーヒー | 選べるグラインド5種 | フレーバーコーヒー
¥1,600
独特の甘く香ばしいキャラメルと ふんわり甘く柔らかいバニラの香りが コナブレンドの風味をより引き立てます 内容量:200g ハワイのアフタヌーンコーヒーをイメージして、香りをブレンドしました。 キャラメル独特の甘く香ばしい香りとバニラの濃密な甘い香りは、安らぎ効果抜群。 ドリップすると、部屋中にキャラメルバニラの香りが広がります。 甘い香りに包まれて、コーヒータイムをより一層癒しの時間としてお楽しみください。 生クリームやチョコレートシロップ・キャラメルシロップで、カフェ風のコーヒーを自宅で手軽に再現できます。 コーヒーの美味しさがより引き立つ、甘さ控えめのお菓子との組み合わせがおすすめ。 ハワイ風に、プレーンパンケーキと一緒にいかがですか? 他のフレーバーコーヒーと同様、ほぼノンカロリー。 ブラックでも甘い香りを楽しめるので、お菓子を我慢しているときの気分転換にもおすすめです。
MORE -

ロイヤルコナコーヒーバニラマカデミアナッツ
¥1,900
ROYAL KONA COFFEE VANILLA MACADEMIA NUT ※こちらは輸入製品です。 ※マークハワイでは、厚生労働省の輸入検査をパスした正規ルート輸入製品のみ取り扱っています。 ハワイのフレーバーコーヒーの代表的存在で、甘い香りと香ばしさがいかにもハワイらしいコーヒーです。 ナチュラルなバニラとマカダミアナッツの香りが豊かに広がる、コナブレンドコーヒーの味をお楽しみください。 これを飲めば、まるで穏やかな南国の風の中にいる気分! ロースト:レギュラーロースト 挽き方:中挽き 内容量:8oz 【ロイヤルコナコーヒー】 農場から直接、最上のグリーン豆のみを仕入れ、ローストマスターにより丁寧かつ完璧に仕上げられ、常に最上のコーヒーを提供。品質と香りが保たれたロイヤルコナは優雅な気分にさせられる。 ワイキキの多くのレストランやホテルに供給、トップシェアを誇る。
MORE -

ロイヤルコナコーヒーバニラクレームブリュレ
¥1,900
ROYAL KONA COFFEE VANILLA CREAME BRULEE ※こちらは輸入製品です。 ※マークハワイでは、厚生労働省の輸入検査をパスした正規ルート輸入製品のみ取り扱っています。 バニラの甘い香りに、香ばしい焼き菓子のようなブリュレの香り。 ハワイ産コナコーヒーのNEWテイストにチャレンジしたフレーバー。香りは強く、ノド越しはマイルドに仕上がっています。 ロースト:レギュラーロースト 挽き方:中挽き 内容量:8oz 【ロイヤルコナコーヒー】 農場から直接、最上のグリーン豆のみを仕入れ、ローストマスターにより丁寧かつ完璧に仕上げられ、常に最上のコーヒーを提供。品質と香りが保たれたロイヤルコナは優雅な気分にさせられる。 ワイキキの多くのレストランやホテルに供給、トップシェアを誇る。
MORE -

マークハワイオリジナルアイスコーヒー・コナブレンド | 選べるグラインド6種
¥1,600
アイスコーヒー用に厳選した豆を、アイスコーヒー用にじっくり焙煎した、マークハワイオリジナルの アイスコーヒーです。 ハワイコナ産ファンシー10%使用のコナブレンド。 長めに焙煎した深煎りなので、やや濃いめに。 氷を入れて、すっきりといかがですか? 内容量:200g 焙煎したての香りとおいしさをお届け! コーヒー専門店が自信を持っておすすめするアイスコーヒーです。 広がる香りと豊かなコクをお楽しみください。
MORE -

ギフトボックス3つ入り用
¥390
レギュラーサイズ専用のギフトボックスです。レギュラーサイズが3つ入ります お中元やお歳暮、贈答用に最適です。 ※のし紙の対応も無料でいたします。選択肢以外の内容はショッピングカート「連絡欄」にご記入ください。
MORE
BEST 3 ITEM